コストセンター?
プロフィットセンター?
今もコンタクトセンターの存在意義についての考え方、意見は様々ありますが、
米国コンサルタントの興味深い記事があったので自身の解釈でまとめました。
なお、このコンサルタントはCXに関する書籍を出版されていたので早速購入、現在翻訳しながら読み込み、要点をまとめています。
英語の理解力が極めて低く相当の時間を要するため、書籍の情報は読破を待たずにCXシリーズで適宜発信します。
長きに渡りブログを更新できませんでしたが、このコンサルタントの記事に書籍、
求めていた答えを探し当てた気分です。
では、AIの力を借りながら記事をまとめてみました。
バリューセンター
「プロフィット」ではなく「バリュー」
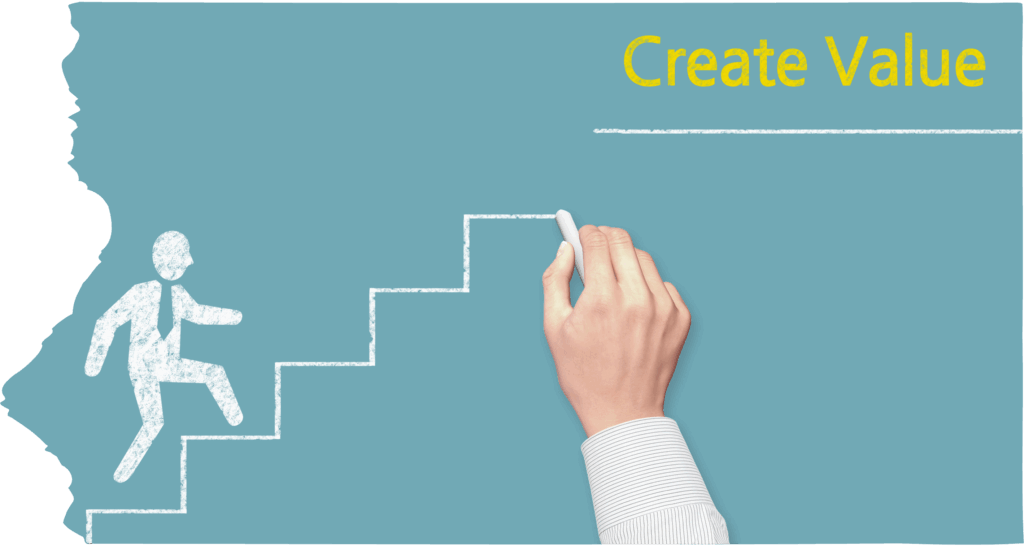
コンタクトセンターのツールは日々進化しています。
では、考え方も進化していますか。
指標に固執し、厳格な階層構造を敷き、能力よりもコンプライアンスを重視する傾向にあり、
時代遅れの感があるのではないでしょうか。
処理時間、通話回数、通話時間は1990年代にとどまっているかのように、ダッシュボード上で依然として目立っています。
これらは主要業績評価指標(KPI)ではなく、環境指標です。
これら数値の価値は、パフォーマンス報告ではなく、WFMが正確な予測を立てるのに役立つことにあります。
単にコール数を数えるだけでなく、コールを原因と結びつけましょう。
・なぜお客様は電話してきたのか?
・連絡のきっかけは何だったのか?
・お客様が電話をするに至った結果の責任者は誰ですか?
・コンタクトセンターはどのような支援を約束し、企業としてどのような対応を約束しましたか?
多くのリーダーは軍隊式で硬直した環境の中で、コンタクトセンター業務に悪いイメージを与えるような時代遅れの管理モデルに固執していました。コンタクトセンターのツールはアップグレードしているものの、考え方は時代遅れのままであり、コンプライアンス、硬直した指標、そして古いプレイブックに固執していることが多く存在しています。コンタクトセンターがその潜在能力を発揮するには単なる「コストセンター」という認識から戦略的な「バリューセンター」へと進化する必要があります。
そのためには、以下の3つの主要領域に重点を置く必要があります。
1.フォーカス
優先順位を明確にし、ビジネス目標を理解し、戦略目標と業務を積極的に連携させましょう。
コンタクトセンターは、他部門の取り組みに盲目的に反応するのではなく、自らの役割を明確に定義する必要があります。
2.可視性
社内プロジェクトへの早期の関与を求め、部門間のパートナーシップを構築し、コンタクトセンターが効果的に準備し貢献するために必要な情報を確実に得られるようにします。
3.メトリクス
データを適切に活用します。
パフォーマンス指標として処理時間などの時代遅れの指標に固執するのではなく、有意義な改善につながるパターンと根本原因を特定します。
さらに、企業の業務運営を徹底的に効率化し、競合他社に対する優位性の確立に向けては、以下の要素で実現性が左右されます。
・需要管理 – コンタクト理由の追跡と、他の部門との合意を正式化すること。
・キャパシティ計画 – ワークフォースの持続可能性を戦略的必要性として扱い、燃え尽き症候群を回避すること。
・テクノロジーの推進 – 技術的な障害を文書化し、より優れたツールの導入を推進するための根拠を示す。
コンタクトセンターのリーダーは、受動的に評価を待つのではなく、明確なデータとビジョンを持って準備を整え、積極的に行動することで、戦略的貢献者としての正当な役割を担いましょう。
記事の主要なポイント
・ツールの進化にもかかわらず、依然として時代遅れの考え方で運営されています
・「コストセンター」から「バリューセンター」への転換が必要です
・優先事項をビジネス戦略全体に整合させる
・変化を受動的に受け止めるのではなく、積極的なパートナーとなる
・データを単なる活動の監視手段ではなく、洞察を得るための手段として活用する
・通話の発信元を追跡し、責任の所在を明確にする
・エージェントのワークロードの持続可能性を確保する
・より良いツールの必要性を文書化し、推進する
コンタクトセンターは、単なるサポート機能ではなく戦略的なプレイヤーとして自らを位置付けるべきです。
戦略的役割を積極的に担う必要があります。
待つのではなく、データを活用し、変化を主導するのです。
ー 以上 ー
コストでもプロフィットでもなくバリュー。
今年、ある大手コンタクトセンターの管理職の方と話をする機会がありました。
とにかく『コスト削減しろ』と上席者から言われているそうです。
典型的なコストセンターの発想。
顧客満足、従業員満足、CXなどと言われている時代に、まだそんなこと言っているんだ、とたまげました。
モチベーションは下がりっぱなしだそうです。
これも現実か。


